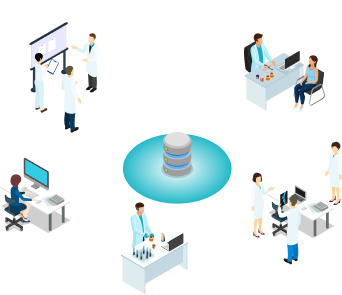ケサンラ点滴静注液350mg
医療用
医療用医薬品:
医師の処方により使用する医薬品
医師の処方により使用する医薬品
医薬品コード(YJコード):1190409A1020
- 収載区分
- 銘柄別収載
- 先発・後発情報
- 先発品(後発品なし)
- オーソライズド
ジェネリック - -
- 一般名
- ドナネマブ(遺伝子組換え)注射液
- 英名(商品名)
- Kisunla
- 規格
- 350mg20mL1瓶
- 薬価
- 66,948.00
- メーカー名
- 日本イーライリリー
- 規制区分
- 劇薬
- 長期投与制限
- 14日(2025年11月末まで)
- 標榜薬効
- アルツハイマー型認知症治療薬〔ヒト化抗N3pGアミロイドβモノクローナル抗体〕
- 色
- -
- 識別コード
- -
- [@: メーカーロゴ]
- 添付文書
-
PDF 2024年11月改訂(第2版)
- 告示日
- 2024年11月19日
- 経過措置期限
- -
- 医薬品マスタに反映
- 2024年12月版
- DIRに反映
- 2024年12月版
- DIR削除予定
- -
- 運転注意
- 情報なし(使用の適否を判断するものではありません)
- ドーピング
- 禁止物質なし(使用の適否を判断するものではありません)
- CP換算
- -
- 長期収載品選定療養
- -
[識別コードの表記 @: メーカーロゴ]
効能効果
アルツハイマー病による軽度認知障害及びアルツハイマー病による軽度の認知症の進行抑制。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 本剤は、疾患の進行を完全に停止、又は疾患を治癒させるものではない。
5.2. 承認を受けた診断方法、例えばアミロイドPET、脳脊髄液(CSF)検査、又は同等の診断法によりアミロイドβ病理を示唆する所見が確認され、アルツハイマー病と診断された患者のみに本剤を使用すること。
5.3. 無症候でアミロイドβ病理を示唆する所見のみが確認できた者、及び中等度以降のアルツハイマー病による認知症患者に本剤を投与開始しないこと。
5.4. 「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、国際共同第3相試験で用いられた診断基準、組み入れられた患者の臨床症状スコアの範囲、試験結果等を十分に理解した上で本剤投与の適否を判断すること〔17.1.1参照〕。
5.5. Flortaucipir(18F)を用いたPET検査の結果から軽度以上のタウ蓄積が認められると判断できない患者に対する有効性及び安全性は確立していない。本剤の投与に先立ち、アミロイドβ病理に関する検査結果、アルツハイマー病の病期、flortaucipir(18F)を用いたPET検査を実施した場合はその結果等を考慮した上で、本剤投与の可否を判断すること。
用法用量
通常、成人にはドナネマブ(遺伝子組換え)として1回700mgを4週間隔で3回、その後は1回1400mgを4週間隔で、少なくとも30分かけて点滴静注する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 安全性上の理由等で本剤1400mgに増量できない場合は、漫然と投与を継続しないこと。
7.2. 本剤投与中にアミロイドβプラークの除去が確認された場合は、その時点で本剤の投与を完了すること。アミロイドβプラークの除去が確認されない場合であっても、本剤の投与は原則として最長18ヵ月で完了すること。18ヵ月を超えて投与する場合は、18ヵ月時点までの副作用の発現状況、臨床症状の推移やアミロイドβプラークの変化等を考慮し、慎重に判断すること〔7.4参照〕。
7.3. アミロイドβプラークの除去は、アミロイドPET検査又は同等の診断法により評価し、検査を実施する場合の時期は本剤投与開始後12ヵ月を目安とすること。
7.4. 本剤投与中は6ヵ月毎を目安に認知機能検査、患者及び家族・介護者から自他覚症状の聴取等による臨床症状の評価を行い、臨床症状の経過、認知症の重症度等から本剤の有効性が期待できないと考えられる場合は本剤の投与を中止すること。なお、本剤投与中に認知症の重症度が中等度以降に進行した患者に投与を継続したときの有効性は確立していない〔7.2、17.1.1参照〕。
7.5. 本剤投与により、アミロイド関連画像異常(ARIA)としてARIA-浮腫/ARIA-滲出液貯留(ARIA-E)もしくはARIA-脳微小出血・ARIA-脳表ヘモジデリン沈着症(ARIA-H)、又は脳出血があらわれることがある〔1.2、2.2、2.3、8.2、8.2.2-8.2.4、11.1.2参照〕。
(1). ARIA-E
MRI画像上重度又は症候性のARIA-Eが認められた場合には、本剤の投与を中断又は中止すること。MRI画像上中等度かつ無症候性のARIA-Eが認められた場合には、本剤の投与を中断すること。MRI画像上軽度かつ無症候性のARIA-Eが認められた場合には、慎重に臨床評価した上で、本剤の投与継続の可否を検討し、投与継続する場合、特に注意深く経過観察すること。
本剤を中断し、ARIAの症状の消失及びMRI検査でのARIA-Eの消失を確認した場合には、投与の再開を検討することができる。
(2). ARIA-H及び脳出血
MRI画像上重度又は症候性のARIA-Hが認められた場合には、本剤の投与を中断又は中止すること。MRI画像上中等度かつ無症候性のARIA-Hが認められた場合には、本剤の投与を中断すること。MRI画像上軽度かつ無症候性のARIA-Hが認められた場合には、慎重に臨床評価した上で、本剤の投与継続の可否を検討し、投与継続する場合、特に注意深く経過観察すること。
本剤を中断し、ARIAの症状の消失及びMRI検査でのARIA-Hの安定化を確認した場合には、投与の再開を検討することができる。
1cmを超える脳出血が認められた場合には、本剤の投与を中止すること。
【参考】
<ARIAの重症度分類:MRI画像による分類>
1). ARIA-E(MRI所見)
①. 軽度:脳溝、皮質、又は皮質下白質の1ヵ所に限局した、5cm未満のFluid Attenuated Inversion Recovery(FLAIR)高信号。
②. 中等度:最大径が5~10cmのFLAIR高信号が1ヵ所にみられる、又は10cm未満の高信号が複数部位にみられる。
③. 重度:10cmを超えるFLAIR高信号で、脳回腫脹及び脳溝消失を伴う。1ヵ所又は複数ヵ所に独立した病変を認める。
2). ARIA-H(MRI所見)
①. 軽度:(脳微小出血)新規が1~4個、(脳表ヘモジデリン沈着症)1ヵ所。
②. 中等度:(脳微小出血)新規が5~9個、(脳表ヘモジデリン沈着症)2ヵ所。
③. 重度:(脳微小出血)新規が10個以上、(脳表ヘモジデリン沈着症)3ヵ所以上。
<ARIA及び脳出血発現時の対応>
1). ARIA-E
①. 無症候性
a. 軽度無症候性ARIA-E:投与継続可能[慎重に臨床評価した上で、本剤の投与継続の可否を検討し、投与継続する場合、特に注意深く経過観察すること]。
b. 中等度無症候性ARIA-E:画像所見消失まで投与中断[MRI検査でのARIA-Eの消失を確認した場合には、投与の再開を検討することができる]。
c. 重度無症候性ARIA-E:画像所見消失まで投与中断[MRI検査でのARIA-Eの消失を確認した場合には、投与の再開を検討することができる]又は中止。
②. 症候性
軽度、中等度、重度症候性ARIA-E:症状及び画像所見消失まで投与中断[ARIAの症状の消失及びMRI検査でのARIA-Eの消失を確認した場合には、投与の再開を検討することができる]又は中止。
2). ARIA-H及び脳出血
①. 無症候性
a. 軽度無症候性ARIA-H:投与継続可能[慎重に臨床評価した上で、本剤の投与継続の可否を検討し、投与継続する場合、特に注意深く経過観察すること]。
b. 中等度無症候性ARIA-H:画像所見安定化まで投与中断[MRI検査でのARIA-Hの安定化を確認した場合には、投与の再開を検討することができる]。
c. 重度無症候性ARIA-H:画像所見安定化まで投与中断[MRI検査でのARIA-Hの安定化を確認した場合には、投与の再開を検討することができる]又は中止。
d. 画像上1cmを超える無症候性脳出血:投与中止。
②. 症候性
a. 軽度、中等度、重度症候性ARIA-H:症状消失及び画像所見安定化まで投与中断[ARIAの症状の消失及びMRI検査でのARIA-Hの安定化を確認した場合には、投与の再開を検討することができる]又は中止。
b. 画像上1cmを超える症候性脳出血:投与中止。
<ARIA及び脳出血発現後のMRIモニタリング>
1). ARIA-E
①. 軽度:ARIA重症化の有無を確認するため、軽度ARIA-Eが無症候性で投与を継続する場合、発現から約1~2ヵ月後にMRI検査の実施を考慮する。軽度ARIA-Eが無症候性で投与を中断する場合、又は症候性の場合は、発現から約2~4ヵ月後にMRI検査を実施し、画像上ARIA-Eの消失が確認されない場合は、追加のMRI検査を実施する。
②. 中等度、重度:中等度、重度ARIA-E発現から約2~4ヵ月後にMRI検査を実施し、画像上ARIA-Eの消失が確認されない場合は、追加のMRI検査を実施する。
2). ARIA-H及び脳出血
①. 軽度:軽度ARIA-Hが症候性の場合、発現から約2~4ヵ月後にMRI検査を実施し、画像上ARIA-Hの安定化が確認されない場合は、追加のMRI検査を実施する。
②. 中等度、重度:中等度、重度ARIA-H発現から約2~4ヵ月後にMRI検査を実施し、画像上ARIA-Hの安定化が確認されない場合は、追加のMRI検査を実施する。
③. 1cmを超える脳出血:画像上1cmを超える脳出血発現後、臨床評価に基づき適宜MRI検査を実施する。
改訂情報
-
医師の処方により使用する医薬品。

 で医薬品を比較する
で医薬品を比較する